ジャズ好きの知人に誘われて、全くの初見で観に行った映画「BLUE GIANT」。最も私が感情移入したのは青春の只中にいる少年たちではなく、それを支える名もなき大人たちだった。
青春の眩しさは痛みを思い出させる
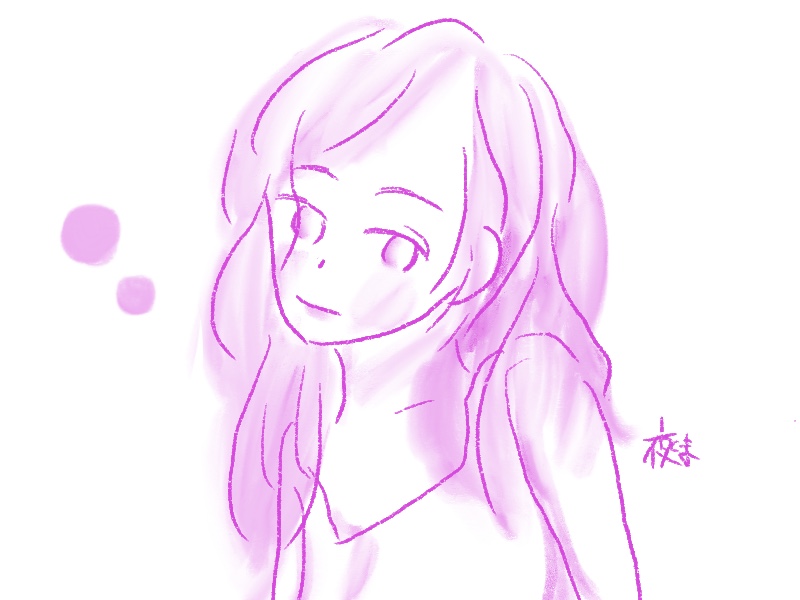
「オレは世界一のジャズプレーヤーになる。」
ジャズに魅了され、テナーサックスを始めた仙台の高校生・宮本大(ミヤモトダイ)。
雨の日も風の日も、毎日たったひとりで何年も、河原でテナーサックスを吹き続けてきた。卒業を機にジャズのため、上京。高校の同級生・玉田俊二(タマダシュンジ)のアパートに転がり込んだ大は、ある日訪れたライブハウスで同世代の凄腕ピアニスト・沢辺雪祈(サワベユキノリ)と出会う。
大は雪祈をバンドに誘う。はじめは本気で取り合わない雪祈だったが、聴く者を圧倒する大のサックスに胸を打たれ、二人はバンドを組むことに。そこへ大の熱さに感化されドラムを始めた玉田が加わり、三人は“JASS”を結成する。
楽譜も読めず、ジャズの知識もなかったが、ひたすらに、全力で吹いてきた大。幼い頃からジャズに全てを捧げてきた雪祈。初心者の玉田。
トリオの目標は、日本最高のジャズクラブ「So Blue」に出演し、日本のジャズシーンを変えること。 無謀と思われる目標に、必死に挑みながら成長していく “JASS”は、次第に注目を集めるようになる。「So Blue」でのライブ出演にも可能性が見え始め、目まぐるしい躍進がこのまま続いていくかに思えたが、ある思いもよらない出来事が起こり……
映画「BLUE GIANT」公式HPより
この映画を見るにあたり、きっかけを与えてくれたのは母だった。
母曰く、「おばちゃんには青臭くてうーんって感じだったけど、アンタはまだ間に合うんじゃない?」とのコメントだった。
結論から言うと、半々である。
青春の熱気の記憶がまだ消え切っていないアラサーの私にとって、それは普段見ないようにしている痛みを刺激する類のものだし、憧れと嫉妬と羨望と、そして、それを超えた眩しさは、応援したくなる光だった。
ちなみに、長々とこんなこと書いてるが、鼻水と涙を垂れ流して、マスクの中で窒息するかと思うほど、それはそれはむせび泣いた。
しっかり、感情移入して、心が動かされた。
世界一を目指す少年を支える人々
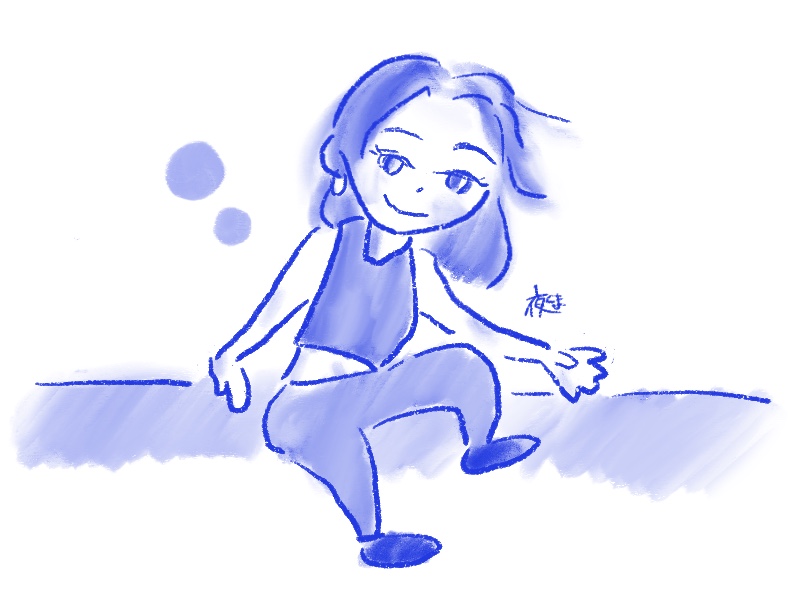
しかし、ここで強調したいのは、どのキャラクターに感情移入したか、ということである。
私が深く感情移入したのは、主役3人の才能溢れる学生たちではなく、彼らを支えて応援し続けた、barのママさんである。
ここではあえて、敬愛を込めて、おばちゃんと呼びたい。
アラサーにして、1番共感したのは、舞台で光り輝く青年達ではなく、それを舞台袖から支援するおばちゃんだった。
こんなおばちゃんになりたいと、心の底から思わされた。なんともかっこよく、凛々しくて、情にあつくて、惚れ惚れする。
ちなみに、余談だが、私は「どんな人に憧れる?」とか、「好きな女優のタイプは?」と聞かれたら、「ハイボールはお好きでしょ、の小雪、または井川遥」と言うことにしている。
たぶん、憂いのある、barのお姉さんが、好きなだけ、という説は、やや否めない。
あんな感じのしっとりしたお姉様になりたいものだ。
つい、筆に熱がこもってしまったが、実はもう1人、感情移入したキャラクターがある。
主人公の青年から、初ライブのビラを街中で受け取る、名も無きサラリーマンの兄ちゃんである。
兄ちゃんは、いかにもうだつの上がらない、冴えないリーマンだが、彼が、主人公たちと出会ってから、みるみるうちに、目に輝きを増していく様子が、私の心までも踊らされた。
百者百様の生き方があって良い

ここまで書いてきて、「お前は一体、何が言いたいんだ?」という話だが、強調したいのは、何もスポットライトの真下でピカピカに光る天才や英雄だけが、人生の主役ではないだろう、ということ。
人生に主役も脇役も、くそったれもないと思っている(その人の人生の主役は誰だって、その人自身のはずだ)
ただ、人の生き方にオンリーワンの正解がないというのが、今回、私が映画から得た尊い学びである。
人には適材適所かあって、向き不向き、得意不得意があるものだ。
特に、このメディアに辿り着いた人なら、尚更、「生きづらさ」や「働きづらさ」を感じている人が多いのではないか。
そんな読者に届けたいメッセージは、100人いたら100通りの生き方があり、それぞれが比べようもなく、かっこよく、美しく、気高いということ。
リーダーを支えるという役割も重要だ

私はかつて、学生演劇に夢中だった。
演劇にはさまざまな役割がある。
私は主に脚本を書き、演出をつける人間だった。
本当の本当は、役者になって、舞台の真ん中で、観客の視線を一身に浴びたかった。
でも、どうしても、セリフやアクションを覚えられず、本番は緊張のせいで、稽古の成果を発揮することはできず、途方もない情けなさと悔し涙を繰り返した。
私が得意なのは、文章を書くことであり、自分の美しいと思う世界を役者やスタッフに熱弁することだった。
でも、一方で、リーダーは向いていなかった。会社で言うところのチームマネジメントはからきし、ダメだった。
演劇をやっていると、脚本演出家および、役者は、少し驕るというか、乱暴な言い方をすれば、調子に乗ってしまうことがある。
でも、衣装・照明・音響・舞台美術・舞台監督・宣伝美術などなど、各分野のスタッフに支えられて、初めて、その演劇作品はお客様の前に現れるのである。
私の好きなワンピース・ルフィの名言に、
「おれは剣術を使えねェんだコノヤロー!!!
航海術も持ってねェし!!!
料理も作れねェし!!
ウソもつけねェ!!」
「おれは助けてもらわねェと生きていけねェ自信がある!!!」第90話「”何ができる”」 / モンキー・D・ルフィ
『ONE PIECE』 第10巻より
ここで語りたいのは、リーダー論ではなく、人にはその人にしかできない役割があって、それを全うすることが、きっと大切な誰かの助けになり得るということだ。
非日常へ小さな一歩を踏み出してみる

ちなみに、余談だが、前述のbarのおばちゃんと、サラリーマンの兄ちゃんの見習うべき点は、「日常から一歩踏み出して、小さなチャレンジをした」ことだ。
それは、今回の映画であれば、主人公たちの応援になるのだろうが、きっかけはもっとささやかな、「赤の他人の少年たちの話を聞いてみる」とか「その演奏を聞きに行く」とか、それくらいの小さなチャレンジだ。
自分の日常の平凡さであったり、ダメさ加減にうんざりした時は、小さなチャレンジや、ちょっとした非日常に身を投じるのはおすすめだ。
私はジャズが何たるかも分からない学生時代に(今もさして詳しくはないが)、作中にも登場するジャズ奏者の聖地「ブルーノート」に、演劇サークルの後輩とコソコソ遊びに行ったことがある。
何かよく分からないけど、格好いい。
言葉にできないけど、ドキドキする。
それは音であり、空間であり、名前も知らない美しいカクテルであり、常連さんたちの楽しそうな横顔であり。
入口でうろうろ迷子になったら、黒人のお兄さんが気さくに話しかけてくれて、ついでにツーショットも撮った。
そしたら、そのお兄さんはドラムの奏者で、ものすごいパフォーマンスをしていて、あれはたまげた。
あの時間が、私の人生に劇的な変化をもたらしたかは分からない。でも、少なくとも、今こうやって、社会人になった今も、あの記憶を愛おしく思い出しながら、この文章を書くに至っている。
これを読むあなたも、ジャズ喫茶、もっと小さな一歩、ジャズのYouTubeはたまた、冒頭の映画を観に行ってみる。そんな小さな挑戦も、たまにはいいかもしれない。
もしかしたら、非日常から振り返った、日常の自分を、もっと好きになるかもしれないから。


